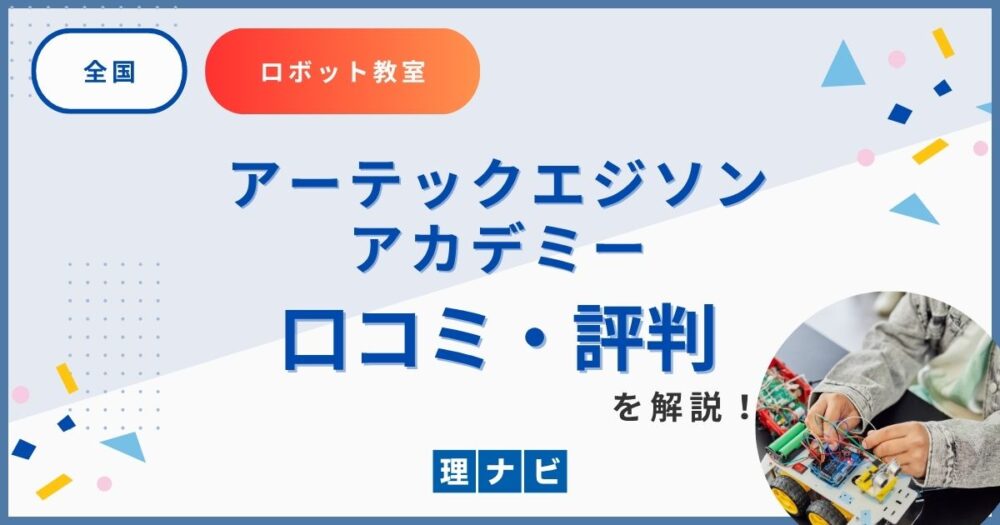
アーテックエジソンアカデミーは、老舗教材メーカー「アーテック」が運営する子ども向けのロボットプログラミング教室で、ブロック型ロボットを使った組み立てとプログラミングの両方を実践的に学べるカリキュラムが特徴です。
初回からプログラミングに取り組める教材設計や、生徒5人に対して講師1人の少人数制、全国に850以上の教室を展開している点が強みとされています。
アーテックエジソンアカデミーは、こんな人におすすめ
・アーテックエジソンアカデミーの口コミが気になる人
・ロボット教室の評判や比較を探している人
・料金や費用感を事前に知っておきたい人
この記事では、アーテックエジソンアカデミーの口コミや評判、料金体系、他の教室との違いや大会(ロボコン)について詳しくご紹介します。
目次
アーテックエジソンアカデミーの口コミ・評判はどう?

アーテックエジソンアカデミーに興味を持ったとき、やはり気になるのは「実際に通っている子どもや保護者の声」ですよね。
このセクションでは、保護者や子どもたちの口コミから見えてくる満足度、よくある感想、他教室との違いについてまとめていきます。
プログラミング教室は明るい雰囲気で子供が楽しく学べていることが実感できます。(googleマップ口コミ/ロボットプログラミングスクール エジソンアカデミー本校)
あきらめずに試行錯誤し、自分で原因を考えて追求する姿勢が見られるようになった。話し方が論理的になり、成長を感じている。家でも子どもが自主的にロボットを組み立てたり、動かしたりして楽しみながら勉強しており、親に作り方を説明してくれたりする。イヤイヤ続けるのではなく、子ども自身が楽しみながら通っているのがよい。(アーテックエジソンアカデミー公式サイトの保護者の声より)
保護者の声:「考える力が伸びた」「家でも話してくれるように」
多くの保護者が実感しているのは、子どもに“考える力”が身についたという変化です。ロボット作りとプログラミングという「正解が1つではない学習」は、子どもたちの発想力や論理的思考を自然と引き出します。
以下のような声がよく聞かれます。
- 「以前よりも『なんでこうなるの?』と自分で考えるようになった」
- 「習ったことを家でも話してくれて、説明が上手になってきた」
- 「説明書通りにやるだけでなく、もっと良くするには?と工夫する姿が見られるように」
また、週1回60分というペースも「ちょうど良い」と好評で、「学校や習い事との両立がしやすい」「毎週楽しみにしている」といった口コミも目立ちます。
子どもたちの反応:「ロボットを動かせるのが楽しい」「ゲームみたい」
通っている小学生たちの反応で多いのは、「ロボットが思い通りに動いたときの達成感が嬉しい」というもの。
- 「自分で作ったロボットがちゃんと動くと、すごくうれしい」
- 「ゲームみたいに楽しくて、1時間があっという間」
- 「友だちのロボットを見るのもおもしろい」
失敗しても「じゃあ次はどうすればいいか」を考える過程が組み込まれており、「失敗がこわくなくなった」という子もいます。
子どもたちは好奇心と達成感をモチベーションにして、自発的に学ぶ姿勢が自然と身についていくのが特徴です。
教室の雰囲気:少人数制で質問しやすい環境
「大人数だと質問しづらい…」という不安を持つ保護者もいますが、アーテックエジソンアカデミーの多くの教室は少人数制。
1クラスは3〜6人ほどの編成が基本で、講師の目が行き届きやすく、子ども一人ひとりの理解度に合わせてフォローが入ります。
- 「うちの子は人見知りなので心配でしたが、すぐに馴染めた」
- 「わからないことがあっても先生がすぐ気づいて声をかけてくれる」
という声も多く、はじめての習い事やプログラミングでも安心して通える点が評価されています。
「うちの子に合ってる」と感じた家庭の共通点
口コミを総合すると、「アーテックエジソンアカデミーが合っている」と感じる家庭には、いくつかの共通点があります。
- 子どもが機械やモノづくりが好き
- ゲームやYouTubeが好きで、それを学びに活かしたい
- 試行錯誤するのが好きで、自分で考えることにやりがいを感じる
- 受け身ではなく、自分のペースで学ばせたい
一方で、すぐに結果を求めるタイプや「正解がないと不安になる」タイプの子どもは、最初に戸惑うことも。ただ、教室のサポート体制が整っているため、徐々に自信を持って学べるようになるケースが多いようです。
保護者同士の情報交換ができる教室も
教室によっては、保護者とのコミュニケーションも大切にしており、定期的な成果発表会や個別面談などが実施されている場合もあります。
- 「子どもが何を学んでいるかが見えて安心」
- 「他の家庭の話を聞いて参考になった」
といった声もあり、単なる“送り迎えだけの習い事”ではない価値を感じている保護者が多い印象です。
アーテックエジソンアカデミーの料金はどれくらい?初期費用・月謝・教材費を解説

習い事を選ぶとき、やはり気になるのは「どれくらい費用がかかるか」という点です。アーテックエジソンアカデミーの料金体系は、教室ごとに多少の差はありますが、共通するおおまかな目安があります。
このセクションでは、入会時に必要な費用や、毎月の月謝、追加でかかる教材費などについて詳しくご紹介します。
初期費用:教材購入があるため少し高め
アーテックエジソンアカデミーでは、入会時に「ロボット教材」を購入する必要があります。これが他のプログラミング教室との大きな違いのひとつです。
- 入会金:5,000円〜10,000円(教室により異なる)
- 教材費:約44,000円(ロボット本体)
ロボット教材は一度購入すれば、その後の講座でずっと使用します。新しい講座のたびに買い替える必要はありません。
教材費が高く感じられるかもしれませんが、「自宅に持ち帰って自由に使える」「家庭でも復習や発展ができる」というメリットがあります。
「高いけれど、長く使えるから納得できる」という口コミも多く見られます。
月謝:1万円前後の教室が多い
アーテックエジソンアカデミーの月謝は、教室によって異なりますが、平均的には月9,000〜12,000円程度です。
- 月謝の目安:9,000円〜12,000円
- 授業回数:月3〜4回(1回60分)
月に3〜4回の授業があり、1回あたりの時間は60分。費用としては、1回あたり2,500円〜3,500円ほどになります。
他のロボット教室と比べても、大きく高すぎるわけではなく、むしろ「家庭で教材を活用できる」ことを考えると、コストパフォーマンスは悪くないと言えます。
また、兄弟割引や紹介特典などの制度がある教室もあるため、入会前に確認しておくとよいでしょう。
教材費は一括払い?分割できる?
ロボット教材の約44,000円という金額について、「一括で払うのは大変」という声もあります。
教室によっては分割支払いに対応している場合があり、月謝と一緒に数千円ずつ支払うスタイルも可能なことがあります。
- 一括払い:多くの教室が基本
- 分割払い:対応している教室もある(例:月4,400円×10回など)
「まとめて払うと負担が大きい」と感じる家庭でも、柔軟な支払い方法が用意されていれば、始めやすくなります。
申し込み前に、各教室の支払い方法を確認しておくと安心です。
オンライン教材や追加費用はある?
基本的に、教材はロボット一式とテキストがセットになっており、追加でかかる費用は多くありません。
ただし、教室によっては、以下のような費用が発生することがあります。
- 年会費(運営費):1,000〜3,000円ほど
- テキスト代:半年ごとに更新される場合もあり(3,000円前後)
- 発表会などのイベント参加費:無料〜数千円
ほとんどの教室では明確に料金が提示されており、突然の追加請求などはないようです。初回の説明でしっかり確認しておくことをおすすめします。
費用に見合った価値はある?
アーテックエジソンアカデミーの費用は「教材がしっかりしている」「家庭でも使える」「子どもの変化が大きい」といった点で、保護者からの満足度は高めです。
口コミでも、
- 「最初は高いと思ったけど、教材が本格的で納得」
- 「ゲームばかりしていた子が、目的を持ってプログラミングに向き合うようになった」
- 「何より、子どもが楽しんで学んでいるのがいちばん」
といった声が目立ちます。
受験や資格を目的にした習い事ではありませんが、「将来に役立つ力を育てる投資」として考えている家庭が多いようです。
アーテックエジソンアカデミーのカリキュラムの特徴は?
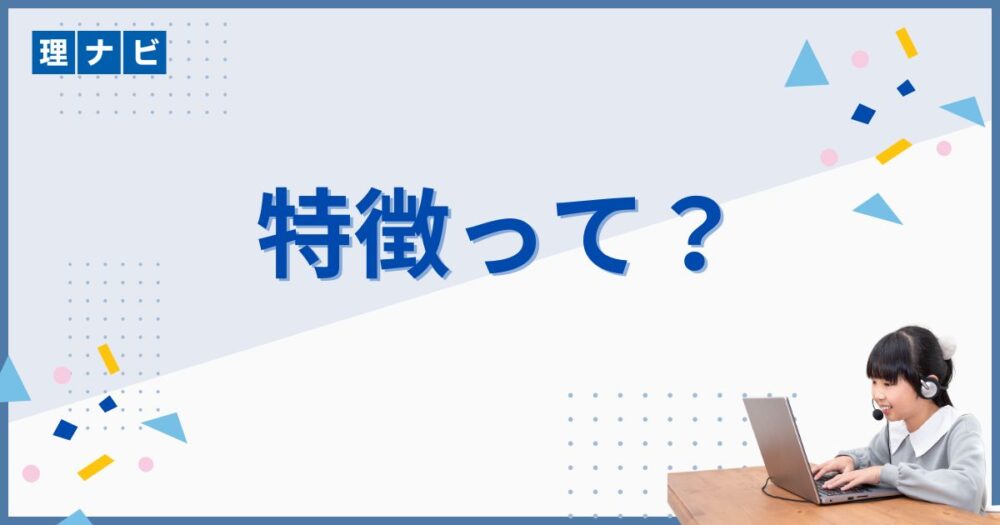
アーテックエジソンアカデミーは、ロボット製作とプログラミングをバランスよく学べるように設計されたカリキュラムが特徴です。子どもたちが「楽しい!」と感じながら、自ら考える力を育てていけるよう、ステップを踏んで学べる仕組みになっています。
このセクションでは、授業の流れ、学習内容のレベル感、どんなスキルが身につくかを詳しく見ていきます。
ロボット制作+プログラミングで構成された授業
授業は毎回、ロボット製作とプログラミングの両方を行います。作って終わりではなく、動かす工程を通して、より深い理解を促します。
- 前半:ロボット製作(組み立て・構造理解)
- 後半:プログラミング(動作設定・テスト・改善)
単なる作業で終わらせず、「なぜこの動きになったのか」「どうすればもっとよくなるか」など、考えながら作業を進めていくことがポイントです。
この構成が、観察力や論理的思考、問題解決力の育成につながっています。
全40回のカリキュラムで着実にステップアップ
アーテックエジソンアカデミーの基本カリキュラムは、全40回(2年間)で構成されています。月2回〜4回の授業ペースで、無理なく継続できます。
- 初級(1〜10回):ロボットの仕組みを理解しながら簡単な動作を実現
- 中級(11〜25回):センサー制御や応用的なプログラムを学習
- 上級(26〜40回):複数の動きを組み合わせた高度な課題に挑戦
初回から本格的すぎる内容にはせず、まずは「楽しい」「できた」を体感させることで、自然にステップアップできる設計になっています。
授業内にプレゼンの時間がある
毎回の授業の終わりには、作ったロボットを使って発表するプレゼンの時間があります。これにより、
- 自分の考えを整理して言葉にする力
- 他の子どものアイデアを聞く力
- 人前で伝える経験
といった非認知能力も同時に育ちます。
「プレゼンがあるから、次回までにもう少し工夫したいと考えるようになった」という口コミも多く見られ、モチベーションアップにもつながっているようです。
テキストは子どもでも読みやすい内容に
カリキュラムに使用されるテキストは、アーテックが独自開発した教材で、カラーの図解が多く、小学生でも理解しやすい構成になっています。
- 組み立て手順が写真付きでわかりやすい
- プログラムの流れをブロックで図解
- 「なぜこうなるか」を考える問いかけが随所にある
テキストを読むだけでも「理解→実践→振り返り」が自然にできるように設計されているため、家庭での復習や一人学習にも活用できます。
Scratchベースのわかりやすいプログラミング
プログラミング部分では、「Scratch(スクラッチ)」をベースにした専用ソフト「Studuino」を使用します。これは、初心者でも直感的に操作できるビジュアルプログラミングで、
- コードを書かずに、ブロックを組み合わせて命令を出す
- ロボットにリアルタイムで動作を反映できる
- テストしながら「失敗→改善」を繰り返せる
といった特長があります。
本格的なコーディングではありませんが、「論理的に命令を組み立てる」トレーニングにはぴったりです。
アーテックエジソンアカデミーの教材ってどう?
アーテックエジソンアカデミーのカリキュラムは、ロボットの組み立てとプログラミングの両方を学べる内容です。教材や授業スタイルにもこだわりがあり、子どもの考える力を自然に引き出す設計になっています。
ブロック組立とScratchベースのプログラミング
授業では、まず専用のロボットキットを使ってブロックの組み立てから始まります。作るロボットは、車・アーム・センサー付き装置などバリエーション豊かで、毎回新しいテーマに取り組みます。
ロボットが完成したら、次にScratchをベースとしたビジュアルプログラミングで動きを設定します。難しいコードは一切なく、小学生でも視覚的に操作を理解できる構成になっています。たとえば「前に動く」「止まる」「ぶつかったら方向を変える」など、具体的な動きをブロックで組み立てる感覚で操作できます。
このように、ロボットとプログラミングの両方に触れることで、手を動かしながら論理的に考える力を身につけていきます。
論理的思考・問題解決力を育てる仕組み
アーテックの授業では、単に動かすだけでなく「なぜうまく動かないのか?」を子ども自身に考えさせるプロセスが重視されています。
・うまく動かなかった理由を考える
・自分のプログラムを見直す
・試行錯誤を通じて修正する
このサイクルを繰り返すことで、自然と原因と結果の関係を理解し、自分で答えを見つけようとする姿勢が育ちます。正解のない課題に挑戦する中で、想像力と創造力も伸ばすことができます。
また、毎回の授業には振り返りシートやチェックリストがあり、保護者も子どもの成長を確認しやすい仕組みになっています。
授業スタイルとサポート体制
授業は1回60分が基本で、月2回からスタートできます。教室によっては月4回や短期講座も選べるため、スケジュールに合わせて通いやすい点も魅力です。
少人数制のクラスが多く、講師が1人ひとりの進度に合わせてサポートしてくれるので、初心者でも安心して参加できます。難しい箇所は講師が一緒に手を動かしながら丁寧に教えてくれます。
教材の持ち帰りや家庭学習用のテキストも用意されており、自宅での復習や兄弟とのシェアも可能です。
アーテックエジソンアカデミーのロボコンって?アーテック主催の大会や実績
アーテックエジソンアカデミーでは、日々の授業に加えて子どもたちの成長を発表する場として「ロボット大会(ロボコン)」が用意されています。参加は自由ですが、多くの子どもが挑戦し、自信や意欲につながっています。
ロボット大会の概要と参加の流れ
アーテックが主催するロボット大会は、年に1〜2回のペースで開催され、全国からエジソンアカデミーの生徒が集まります。予選から本戦までのステップがあり、地域別の予選を勝ち抜いたチームが本選に出場する形式です。
課題は毎年変わり、たとえば「ラインに沿って自動走行する」「物を運んで正確に置く」などの実用的な内容が用意されます。どれも論理的な構成と精密なプログラミングが求められるため、自然と学びのモチベーションが高まります。
大会の申し込みは各教室から行え、教室によっては出場チームの選考会や練習会が用意されているところもあります。
子どもたちのモチベーションにつながる仕組み
大会に向けた練習は、通常の授業よりもさらに「自分で考える力」が求められます。
たとえば、
- どうすれば課題を効率よくクリアできるか
- プログラムを短く、正確に作るにはどうすればよいか
- チームでどのように分担して取り組むか
このような問いに取り組む中で、子どもたちは自然と「やってみたい」「もっと良くしたい」という気持ちになります。
また、大会当日には他教室の生徒のアイデアや工夫に触れられるため、視野も広がります。「次はもっと上を目指したい」という前向きな気持ちが育つ貴重な機会です。
保護者の方からも「大会を経験してから、授業への取り組み方が変わった」「子どもが自信を持つようになった」といった声が多く聞かれています。
実際の入賞例と実績
過去の大会では、小学3年生が作ったロボットが「自動配達マシン」として注目された例や、小学生の兄弟がペアで挑み入賞した事例など、年齢や経験に関係なく努力が報われる環境が整っています。
また、アーテック主催の大会は、教育関係者の注目度も高く、子どもたちの実績として将来的にポートフォリオに活用することも可能です。
こうした大会の存在が、日常の学びを「実際に活かす場」へと変えてくれる点も、エジソンアカデミーならではの魅力です。
アーテックエジソンアカデミーが向いている子どもはどんなタイプ?
アーテックエジソンアカデミーは、すべての子どもに合うわけではありません。どんな子に向いているのか、どんな家庭におすすめなのかを具体的に確認していきましょう。
向いている年齢や性格のタイプ
エジソンアカデミーの推奨開始年齢は、小学3年生以上。Scratchベースのプログラミングや、複雑な組み立てに挑戦するため、一定の読み書き力と集中力が必要です。
以下のようなタイプの子どもには特に向いています。
- ブロック遊びが好きで、仕組みに興味がある
- ゲームや機械の中身を知りたがる
- 自分のアイデアを形にするのが好き
- 論理的に考えることにワクワクできる
- 人前で発表するのに抵抗が少ない、または挑戦したい気持ちがある
一方、まだ机に長く座ることが難しい年齢の子や、「動かす」よりも「絵を描く」などの表現活動が得意なタイプの子には、もう少し違ったアプローチの教室のほうが合う可能性もあります。
保護者が気をつけたい家庭でのサポートの視点
エジソンアカデミーでは、教室だけで完結する学びではなく、家庭でのフォローも大切です。子どもがうまくいかずに落ち込んで帰ってきたとき、すぐに答えを与えるのではなく「どうしたの?」「次はどうしたい?」と寄り添う姿勢があると、子どものやる気を支えられます。
また、課題によっては持ち帰りの復習があることもあるため、少しずつ進捗を見守るゆとりがあると、より安心して取り組めます。
無理に親が教える必要はありませんが、関心を持って応援してあげるだけでも、子どもの自信につながります。
向いていない場合に検討したい他教室の選び方
もし「ロボットよりもゲームが好き」「Scratchが難しそう」と感じた場合は、以下のような教室も候補になります。
- マインクラフトを使って楽しく学べる教室
- iPadでビジュアルプログラミングができる入門スクール
- オンラインでゆっくりマイペースに学べるプランがある教室
子どもの「好き」の方向性によって、適切な教室は異なります。体験授業などを通して、教室の雰囲気や教材との相性をしっかり見極めていくことが大切です。
まとめ:アーテックエジソンアカデミーはこんな家庭におすすめ
アーテックエジソンアカデミーは、「ロボット」と「プログラミング」の両方に興味がある子どもにとって、学びが深まる絶好の環境です。Scratchベースのカリキュラムは初学者にも親しみやすく、実際に手を動かすことで論理的思考や問題解決力が育ちます。
さらに、ロボット大会のようなアウトプットの機会も用意されているため、目標を持って継続しやすいのも大きな特徴。成績や受験だけでは測れない「考える力」や「やりぬく力」を育てたいと考えるご家庭に、特におすすめです。
こんな家庭に向いています!
- 遊び感覚で楽しく学びながら、確実にスキルをつけさせたい
- 単なる暗記よりも、考える力や発表力を身につけさせたい
- 家でも子どもの取り組みを見守りながら、一緒に成長を感じたい
反対に、「もっと気軽にプログラミングを始めたい」「まだ低学年で集中力に不安がある」という場合は、他のやさしい入門スクールからスタートするのも選択肢のひとつです。
とはいえ、まずは教室の雰囲気や子どもとの相性を確認することが大切です。無料体験ができる教室も多いため、気になる方は一度足を運んでみることをおすすめします。
